2025/04/30 / 社内業務効率化

読書の新しいスタイルとして注目を集める「オーディオブック」。通勤時間や家事の合間など、スキマ時間を有効活用できるのが大きな魅力です。近年はAI音声合成技術の進化により、プロのナレーターによる朗読だけでなく、著者本人や好みの声で聴ける作品も登場しています。
この記事では、オーディオブックのメリット・デメリット、AI音声合成がもたらす変化について解説します。AI音声合成のおすすめソフトもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
オーディオブックとは、書籍を音声化したもので、いわば「耳で聴く本」です。スマートフォンやタブレットなど、インターネットに接続できるデバイスがあれば、いつでもどこでも手軽に読書を楽しむことができます。
小説、ビジネス書、自己啓発書、児童書など、多様なジャンルの書籍がオーディオブック化されており、読書の新たなスタイルとして人気を集めています。
オーディオブックには、従来の読書スタイルにはないさまざまなメリットがあります。生活に取り入れることで、より豊かな読書体験が得られるでしょう。
いつでもどこでも「ながら聴き」ができるため、スキマ時間を有効活用できるのがオーディオブックの大きなメリットです。満員電車での通勤・通学時間、家事の合間、ウォーキングやジョギング中など、これまで「何もできなかった時間」が「貴重な読書時間」に変わります。
ウォーキング中に小説の世界に浸ったり、朝の支度中にニュースや英語学習コンテンツを聴いたり。限られた時間を最大限に活用できるツールとなるでしょう。
オーディオブックは再生速度を調整できるため、自分のペースで読書を楽しめます。たとえば、移動時間や休憩時間などのスキマ時間を活用して、1.5倍速や2倍速で聴くことで、効率よく情報を得られます。
一方、複雑な内容を理解したいときや重要な箇所は速度を落として繰り返し聴いたり、ストーリー展開を楽しみたい小説は標準速度で聴いたりと、目的に合わせて再生速度を変えられます。
オーディオブックは「耳で聴く読書」のため、活字を読むのが苦手な人でも親しみやすいメリットがあります。感情豊かな朗読は物語の世界観に没頭しやすく、想像力をかき立てられるでしょう。
また、視覚障がいのある人にとっても、オーディオブックは読書の新たな可能性を広げるツールとなります。点字訳や音訳サービスに加え、オーディオブックという選択肢が加わることで、より多くの作品に触れられるようになり、読書の楽しみ方がグッと広がります。
オーディオブックのメリットの一つに、音声コンテンツだからこそできる反復学習の容易さがあります。繰り返し聴くことで、情報が自然と記憶に定着していくため、勉強や暗記に効果的です。
また、語学学習にも、オーディオブックが活躍します。ネイティブスピーカーの発音やイントネーションを繰り返し聴くことで、自然な語感が身につくでしょう。
オーディオブックを聴きながら運動することで、脳機能の向上や認知症予防に効果がある可能性が示唆されています。
関西福祉科学大学は、ベルピアノ病院との共同研究で、65歳以上の要支援高齢者を対象に脳血流の活性作用を検証しました。
①運動のみ
②オーディオブック×運動
③計算課題×運動
以上の3条件で脳血流反応を比較した結果、オーディオブックを聴きながら運動した場合、計算課題をしながら運動するのと同等の脳血流活性作用が見られたといいます。
従来の認知症予防トレーニングでは、計算やしりとりなどがよく用いられてきましたが、種類が限られるという課題がありました。その点、オーディオブックは多様なコンテンツを楽しめるため、飽きずに続けられるというメリットがあります。
この研究結果を受け、ベルピアノ病院の通所リハビリテーションセンターでは、2022年4月から認知症予防のツールとして、高齢者の運動課題にオーディオブックを導入しています。
出典:オーディオブック×運動に、認知症予防トレーニングと同等の脳血流活性作用を発見|audiobook.jp
スマートフォンやパソコンの画面を長時間見続ける現代人にとって、目の疲れは深刻な問題です。オーディオブックは目を休ませながら読書を楽しめるため、目の負担軽減につながります。また、落ち着いたナレーションはリラックス効果をもたらし、就寝前の読書にも最適です。
オーディオブックはデジタルデータのため、場所を取らず、整理整頓も簡単です。多くの書籍をデバイス一つに保存できるため、引っ越しや断捨離の際も手を煩わせることがありません。また、一つの場所に集約されているため、読みたい本を探す手間も省けます。
オーディオブックは、複数人で一緒に聴くことも可能です。例えば、家族でドライブ中に同じ物語を楽しんだり、友人との勉強会でオーディオブックを聴いたりと、さまざまな活用法があります。
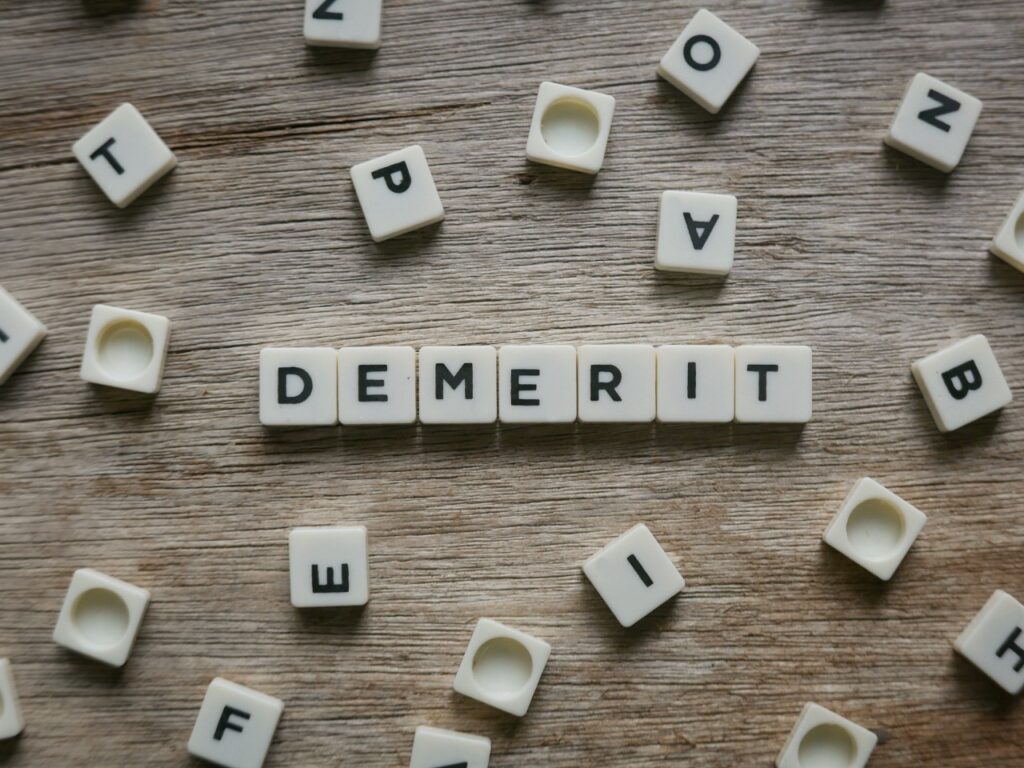
オーディオブックは便利なサービスですが、デメリットも存在します。利用前に、デメリットを把握しておきましょう。
紙の本であれば、気になったページをすぐに読み返せます。しかし、オーディオブックは時間の感覚を頼りにしなければならないため、聞きたい箇所をピンポイントで探し出すのが難しい場合があります。
再生速度調整機能や巻き戻し機能をうまく活用しましょう。また、メモアプリなどを併用して、気になった箇所の時間やキーワードを記録しておくのもおすすめです。
すべての書籍がオーディオブック化されているわけではありません。特に、専門書やニッチな分野の書籍は、オーディオブック版がない場合が多いです。読みたい本がオーディオブックで提供されていない場合は、デメリットといえるでしょう。
書籍を聴取したい場合は、電子書籍リーダーの読み上げ機能を利用するという方法もあります。
オーディオブックは音声データのため、直接書き込みができません。紙の本に線を引いたり、メモを書き込んだりすることが好きな人にとっては、物足りなく感じる場合があります。
覚えておきたいところは、メモアプリなどを活用して、感想や重要なポイントを記録しましょう。音声再生ソフトにブックマーク機能がある場合は、活用すると便利です。
オーディオブックは、ナレーターによって作品の印象が左右されます。ナレーターの声や朗読スタイルが自分の好みに合わないと、作品を楽しめない可能性があります。
サンプル音声を聴いて、ナレーターの声や朗読スタイルを確認してから購入することが大切です。
オーディオブックは「ながら聴き」ができる反面、集中して聴かないと内容が頭に入ってこない場合があります。また、リラックスして聴いていると眠くなってしまう人もいるでしょう。
集中して聴きたい場合は、周囲の雑音を遮断できる環境で聴きましょう。また、再生速度を調整するのも効果的です。
AI音声合成技術は、オーディオブック制作に変化をもたらし、ユーザーと制作者双方に多くのメリットを提供しています。
従来のオーディオブック制作は、プロのナレーターの起用、スタジオ収録、音声編集など、多大なコストと時間を要していました。その点、AI音声合成を活用することで、これらのプロセスを省いて、高品質な音声が生成されます。
出版にあたっては、読み間違い(イントネーション違い、特に固有名詞や専門用語の間違い)がないか、専門スタッフによる丁寧なチェックと調整が行われています。オーディオブックは単なるテキスト読み上げにとどまらず、耳からの情報取得に最適化された自然で聞き取りやすい音声に仕上げられています。
AI音声合成を活用することで、制作コストと工数を削減しつつ、高品質なオーディオブックをより早く、より低価格で提供することが可能になります。
自然な声質のAI音声合成ソフトについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
AI音声合成技術は、声質、抑揚、感情表現などの音声調整を可能にします。制作側にとっては、特定のイメージに合った声質や話し方を選択できるため、作品の世界観に寄り添った表現が可能になります。
一方、ユーザー側にとっては、パーソナライズされた読書体験を実現する可能性を秘めています。ゆっくり聴きたい、早く聴きたいなど、速さを調節できるのはもちろん、複数人の話者を選択できる場合は、好みの声質や口調で、オーディオブックを楽しめるようになるかもしれません。
AI音声合成技術を使えば、著者本人の声でオーディオブックを制作することも可能です。
従来は、著者が時間を確保してスタジオ収録を行う必要がありました。しかし、AI音声合成を活用することで、比較的短い収録時間の音声データライブラリから著者の声の特徴を学習し、自然な朗読音声を生成できます。そのため、著者に過度の負担を強いることなく、本人の声で作品を届けることができます。
ユーザーは著者本人の声で聴くことで、まるで著者がすぐ隣で語りかけているような親密な読書体験となります。作品世界への没入感が高まり、より深く物語を味わえるでしょう。

AItalk®は、高品質なAI音声合成エンジンとして、オーディオブック制作に影響を与えています。従来、オーディオブックの制作には、プロの声優やナレーターによる収録、スタジオの手配、編集作業など、多くの時間と費用が必要でした。しかし、「AItalk®」を活用することで、これらのコストと時間を削減できます。
「AItalk®」は、深層学習技術に基づく音声合成方式を採用し、より自然で滑らかな音声を実現しています。音声の速度や高さ、抑揚などを細かく調整できるため、表現力豊かな朗読が可能です。臨場感あふれる音声は、オーディオブックの可能性を広げる要素となるでしょう。
[ 資料ダウンロード ]
[ お問い合わせはこちら ]
フライヤー社はこれまで、書籍の要約をテキストで提供していましたが、移動中でも手軽に楽しめるように、また活字が苦手な方にも使いやすくするために、音声版の配信を始めました。この音声版の制作には、自然で高品質な音声を作れる「AITalk® 声の職人(パッケージ版)」が使われています。
「AITalk® 声の職人」は、テキストを入力するだけで手軽に音声ファイルを作成できるのが特徴です。電子書籍、eラーニング、動画などのデジタルコンテンツのナレーション作成はもちろん、電話自動応答音声や製品ガイダンス音声の作成にも利用できます。
直感的な操作で、高品質な合成音声を誰でも簡単に作成できるため、オーディオブック制作のハードルを大きく下げられるでしょう。
参照:お客様事例|話題の本が音声で聴ける! 書籍要約サービス「flier(フライヤー)」に エーアイの音声合成AITalkが採用
オーディオブックのメリット・デメリットを紹介してきました。「時間の有効活用」「内容の定着率の高さ」などさまざまなメリットがある中、AI音声合成は、オーディオブックの可能性を大きく広げる可能性を持っています。AI音声合成を活用することで、オーディオブック制作のコストを削減でき、より多くの作品を、より早く、そしてより手軽に制作・配信できるようになります。
AI音声合成技術の進化は、オーディオブックの制作・配信方法を大きく変え、より多くの人々が読書を楽しむ機会を提供するでしょう。より豊かな読書体験のために、AITalk®は今後も自然で表現力ある音声合成を目指しています。
[ 資料ダウンロード ]
[ お問い合わせはこちら ]
「AITalk® Custom Voice®」は、芸能人や声優、自分の声を収録し、日本語音声合成用のオリジナル辞書を作成するサービスです。
文字を入力するだけで、本人の声のようなリアルな音声で喋らせることができるので、WEBキャンペーンや、スマートフォンのアプリケーション、ゲーム、バーチャルキャラクター、テレビ番組等で、インパクトのある音声コンテンツを実現できます。
聴くHPでアクセシビリティアップ!Webサイトにタグを埋め込むだけで、簡単に今あるWebサイトが音声読み上げ機能つきのサイトに変わります。
AITalk® 声の職人® クラウド版は、テキストをブラウザに入力するだけで誰でも簡単にナレーションや、ガイダンス音声を作成することができるクラウドサービスです。
月額プランで契約できるので、低予算で検討している方や、少しだけ音声ファイルを作りたい方におすすめの音声合成クラウドサービスです。