2024/12/20 / 社内業務効率化

動画を社員研修や業務マニュアルに活用する企業が、小売業、製造業、介護関連などを中心に増えています。
研修動画は、時間や場所に縛られず、視覚と音声で効率よく情報を伝えられるため、従来の研修形式を補完する新たな手段として注目されています。
特にリモートワークが普及した現在、社員が自分のペースで学べる研修動画は、スキルアップや業務効率化に大きく貢献するでしょう。
本記事では、研修動画のメリットやデメリット、制作のポイントや事例を紹介します。
研修動画とは、従来の対面研修やテキスト教材とは異なり、教育やトレーニングを目的とした映像コンテンツを指します。
動画で研修内容を伝えることで、受講者にとって理解しやすく、効率的に学習内容を定着させられるのが特徴です。
さらに、インターネットを活用した「eラーニング」との相性も良く、時間や場所を問わず受講できる点が大きなメリットです。
その利便性の高さから、多くの企業が研修プログラムに動画を採用するなど注目を集めています。
ここでは研修動画のメリットを紹介します。研修に課題を感じている企業担当者は、内容を理解したうえで導入を検討してみてください。
研修動画は、研修にかかるコストの削減に役立ちます。初期段階では制作費が必要ですが、一度作成すればその後の費用はほとんど発生しません。
従来の対面型や集合研修では、会場費、交通費、講師への人件費や外注費など、さまざまなコストがかかっていました。研修動画を導入すれば、これらを大幅に削減できます。
中長期的に見ると、動画研修は経済面でも大きな効果が期待されます。
研修動画は、インターネット環境があれば、時間や場所にとらわれず受講できます。
例えば、製造業の機械操作や介護施設での研修など、これまでは集合形式が前提だった内容も、パソコンがあれば個別に受講可能です。受講者が自分の都合に合わせて時間や場所を選べる点は、大きな利点と言えます。
また、テレワークを導入している企業でも、動画を活用すれば教育の質を維持でき、リモート環境でも効果的な研修が実現します。こうした特長から、動画研修は現代の働き方に適した手法として注目されています。
研修動画には、高品質な研修を安定して提供できるという利点もあります。
対面や集合型の研修では、講師によって内容や指導方法にばらつきが出ることがありますが、動画ならそのような差が生じません。すべての受講者が同じ内容を学べるため、「講師によって言うことが違う」といった不満も解消されます。
特に、複数の拠点を持つ大企業では、企業理念や社会人マナー、マネジメントなどの研修において講師の質が成果に直結します。動画を活用すれば、その効果をより確実に引き出せます。
研修動画は、繰り返し視聴できる点も大きなメリットです。
一度では理解が難しい内容も、繰り返すことで定着が期待されます。必要な部分だけを選んで視聴すれば、効率的に学習を進められます。
業務マニュアルなどを扱う場合は、理解度を確認するためにテストやアンケート、レポートを組み合わせることで、さらに定着率を高められます。
対面型や集合型の研修では、実施のたびに講師の手配、会場の確保、教材の準備が必要になります。人事担当者が通常業務と並行して対応する場合、手間やコストの負担は避けられません。
一方、研修動画は一度制作すれば何度でも活用でき、新入社員の入社や人事異動で新たなメンバーが加わっても、接客マナーや社内システムの動画を共有するだけで対応可能です。
こうした効率性の高さも、研修動画の大きな利点です。
研修動画には多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。
研修動画の作成には、一定のコストや手間がかかる点がデメリットです。
すべて自社で制作すれば費用は抑えられますが、ノウハウが不足している場合は、品質の低下や制作の遅れが生じる恐れがあります。
そのような場合は、専門の制作会社に依頼するのが現実的な選択です。ただし、外注では初期費用が高くなり、打ち合わせや調整の手間も避けられません。
自社制作と外注、それぞれの負担を比較し、自社の状況に応じた方法を選ぶことが重要です。
研修動画は人との直接的な関わりがないため、参加者同士で切磋琢磨したり、新たな人間関係を築いたりする機会が限られるという課題があります。
その対策として、チャットグループやメンバー一覧を設け、受講者同士の交流を促す仕組みを取り入れると効果的です。こうした環境を整えることで、意見交換や情報共有が活発になり、研修動画の効果向上にもつながります。
研修動画では講師が受講者の反応を直接確認できないため、理解度に応じた対応が難しいという課題があります。
一方的な情報提供に終始しないよう、研修中に問いかけを挟んだり、終了後にテストやレポート、アンケートを行ったりする工夫が効果的です。こうした対応により、理解度を把握しながら内容の見直しにもつなげられます。
研修動画の導入は、業種や規模を問わず多くの企業にメリットがありますが、とくに全国に拠点を展開している企業や在宅勤務・リモートワークを導入している企業におすすめです。時間や場所にとらわれず受講できるため、全社員へ均一な内容を効率的に届けられます。これにより、集合研修にかかる交通費や会場費などのコスト削減が可能となり、業務への負担を最小限に抑えながら教育を行えます。
また、研修動画は必要に応じて繰り返し視聴できるため、理解が不十分な箇所を個々で補完でき、知識の定着率向上にも効果的です。新人研修やコンプライアンス教育、製品知識の習得、マネジメント研修など幅広いテーマに対応でき、部署や役職に合わせた柔軟な教育カリキュラムを構築できます。
さらに、動画教材は一度制作すれば複数回活用できるため、長期的に見ても高い費用対効果を発揮します。教育担当者の負担軽減にもつながり、研修の品質を安定させられます。業務効率化と人材育成の両立を図りたい企業にとって、研修動画は非常に有効なツールといえます。
動画マニュアルの作成法については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
研修動画を成功させるためには、以下の3つのポイントを押さえましょう。
まず研修動画の目的とターゲットを明確にします。「何のために」「誰に向けて」の動画かを具体的にすることで、方向性をはっきりさせることができます。
コンテンツの構成を考える際は、動画のテーマを1つに絞ることで、受講者に「何を学んでいるのか」を意識させやすくなります。
研修動画は、1本あたり5~10分の長さにすることで、受講者は集中力を保ちやすくなり、学習効果が高まるでしょう。研修内容が多岐にわたる場合は、いくつかのステップに分けて複数の動画を作成することをおすすめします。
研修動画における音声(ナレーション)は、視聴者の理解度を大きく左右する重要な要素です。音声を効果的に活用することで、研修内容が受講者にとって分かりやすくなるだけでなく、記憶にも定着しやすくなります。
さらに、研修動画におけるナレーションに「AI音声合成」を活用することで、効率的に作成できるだけでなく、品質を一定に保てるようになります。AI音声合成とは、テキストをもとに、AIが自動的に人のような音声を生成する技術です。
AITalk®は、自然な日本語の発音に加え多彩な話者をそろえており、研修動画の制作におすすめです。下記ではデモを聞けますので、ぜひ試してみてください。

[デモを試してみる]
AI音声合成ソフトについては、以下の記事でも詳しく解説しています。併せてお読みください。
ここからは、AI音声合成を活用した研修動画の事例を5つ紹介します。
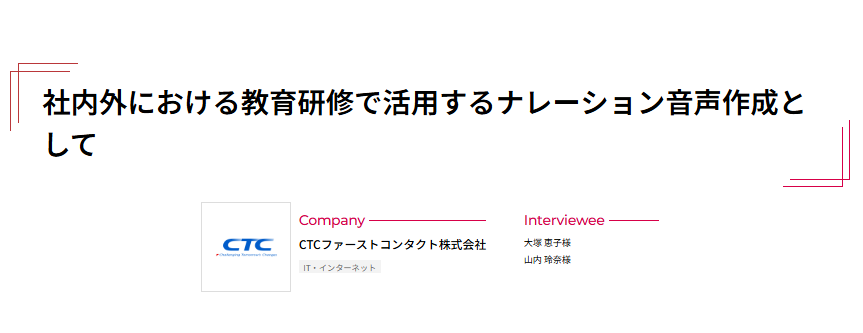
CTCファーストコンタクト株式会社様では、研修動画を自社で制作していましたが、「ナレーションの練習に手間がかかる」「周囲の雑音で収録が進まない」といった課題を抱えていました。
そこで「AITalk®」を導入した結果、ナレーション作成をPC上で完結できるようになり、読み上げの練習や再収録にかかっていた工数を削減しています。
さらに、社外向けや復習用に動画を配布する際に問題となっていた肖像権の課題も解消され、スムーズな提供が可能になりました。

弥生株式会社様は、「講師によるビジネスマナー研修では品質にばらつきがあり、内容が伝わりにくい」という課題を抱え、オンライン研修への移行とセルフ学習の手段を検討していました。
講師の話す内容を「AITalk®」でナレーション化し、パワーポイントのスライドを動画にしたことで、品質を一定に保った研修を実現しています。この取り組みにより、安定して高品質な動画研修の提供が可能となりました。

大鵬薬品工業株式会社様では、社内コンプライアンス教育の一環としてデジタル教材を配信しており、社外から購入した教材に加えて大量のパワーポイント資料も活用していました。これらにナレーションを加え、動画研修化する方針を検討していました。
しかし、収録に不慣れな社員の声では聞き取りづらく、時間や場所の確保にも課題がありました。
そこで「AITalk®」を導入した結果、約8時間かかっていた収録作業が約2時間に短縮され、大幅な効率化を実現しています。

アサヒ飲料株式会社様では、新メンバー向けに自社製品の品質に関する研修動画を作成しており、パワーポイントを用いた動画を制作していました。しかし、在宅勤務による録音環境の不備や、読み間違いによる再収録といった課題が発生していました。
「AITalk®」導入後は、音質のバラつきや読み間違いなど、人による収録時の問題をすべて解消。AI音声でありながら自然な仕上がりで、聞き取りやすさや品質の高さに効果を実感しているとのことです。

横浜国立大学様では、大学の広報動画や情報セキュリティ教育教材の制作を検討していました。ダイバーシティの観点から字幕やナレーションの追加を進めようとしたものの、プロに依頼すると修正時の対応が難しいという課題がありました。
導入前は「プロのナレーターでなければ満足できない」という意見も多くありましたが、「AITalk®」の自然な音声を活用して動画を制作した結果、多くの方がその品質に好印象を持つようになりました。
事例で紹介した通り、研修動画の導入は、制作コスト削減や知識の定着に効果があり、多くのメリットが期待されます。一度作成した動画は繰り返し活用でき、研修業務の効率化にもつながります。
本記事の事例を参考に、自社に合った研修動画の体制構築を検討してみてください。またAI音声合成を取り入れることで、より効率的で効果的な研修動画が実現します。
動画研修の音声に関するお悩みがあれば、ぜひエーアイまでご相談ください。高品質なAI音声で、動画制作をしっかり支援いたします。
AITalk® 声の職人® クラウド版は、テキストをブラウザに入力するだけで誰でも簡単にナレーションや、ガイダンス音声を作成することができるクラウドサービスです。
月額プランで契約できるので、低予算で検討している方や、少しだけ音声ファイルを作りたい方におすすめの音声合成クラウドサービスです。